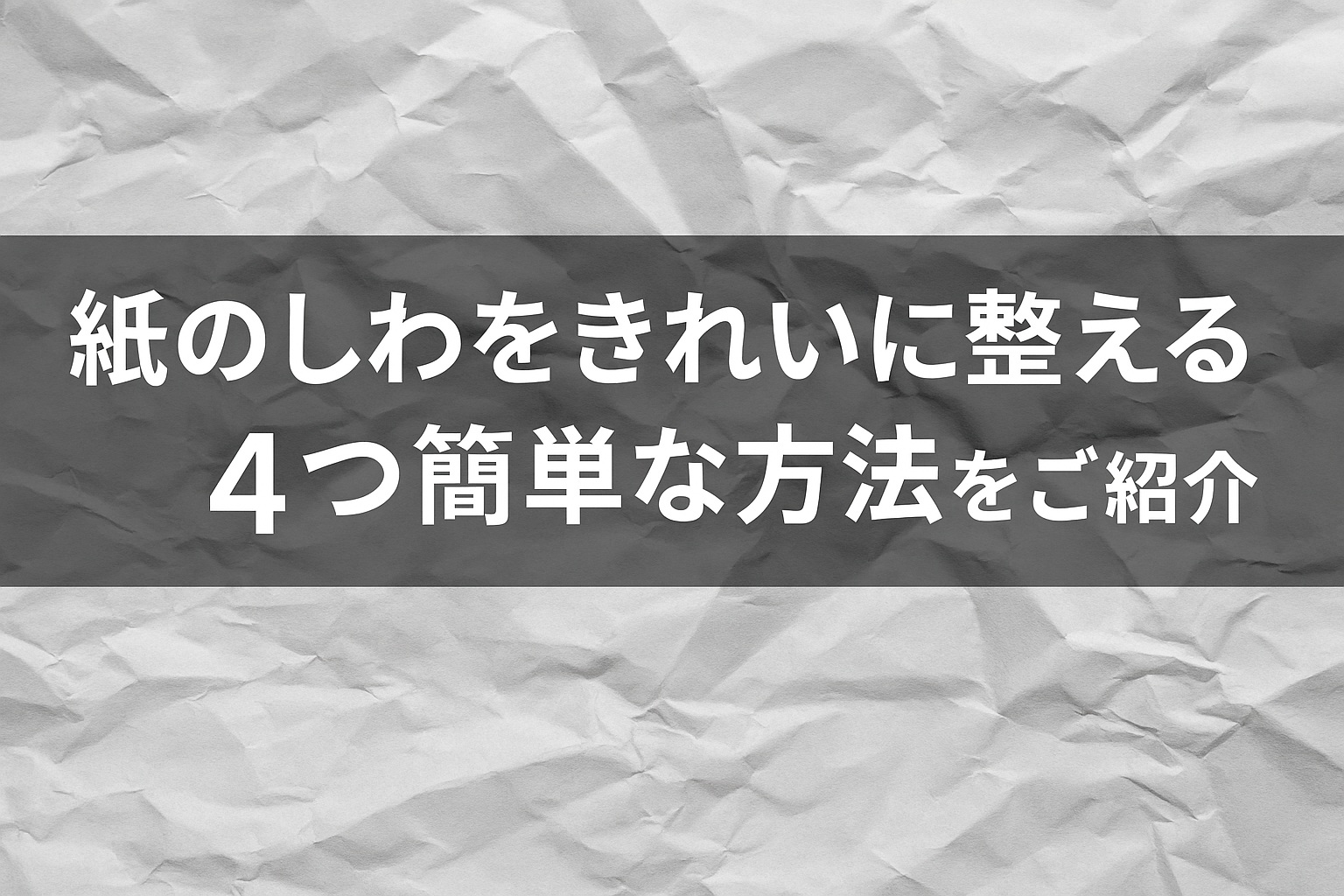気がつくと、大事な書類や申請書がしわだらけになっていて焦ったことはありませんか?
特に大切な書類の場合、見た目が気になると何とか元に戻せないか悩んでしまいますよね。
「少しでもきれいに直せたら…」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
実は、そんなときに役立つ、紙のしわを整えるちょっとしたコツがあるんです。
今回は、いざというときに試してほしい、簡単で便利なしわ取りの方法を4つご紹介します。
新品のように完全に元通りとはいかないかもしれませんが、人前に出しても恥ずかしくないくらいに整えることができます。
ぜひお試しになってみてくださいね。
紙のしわをきれいに整える4つの簡単テクニック
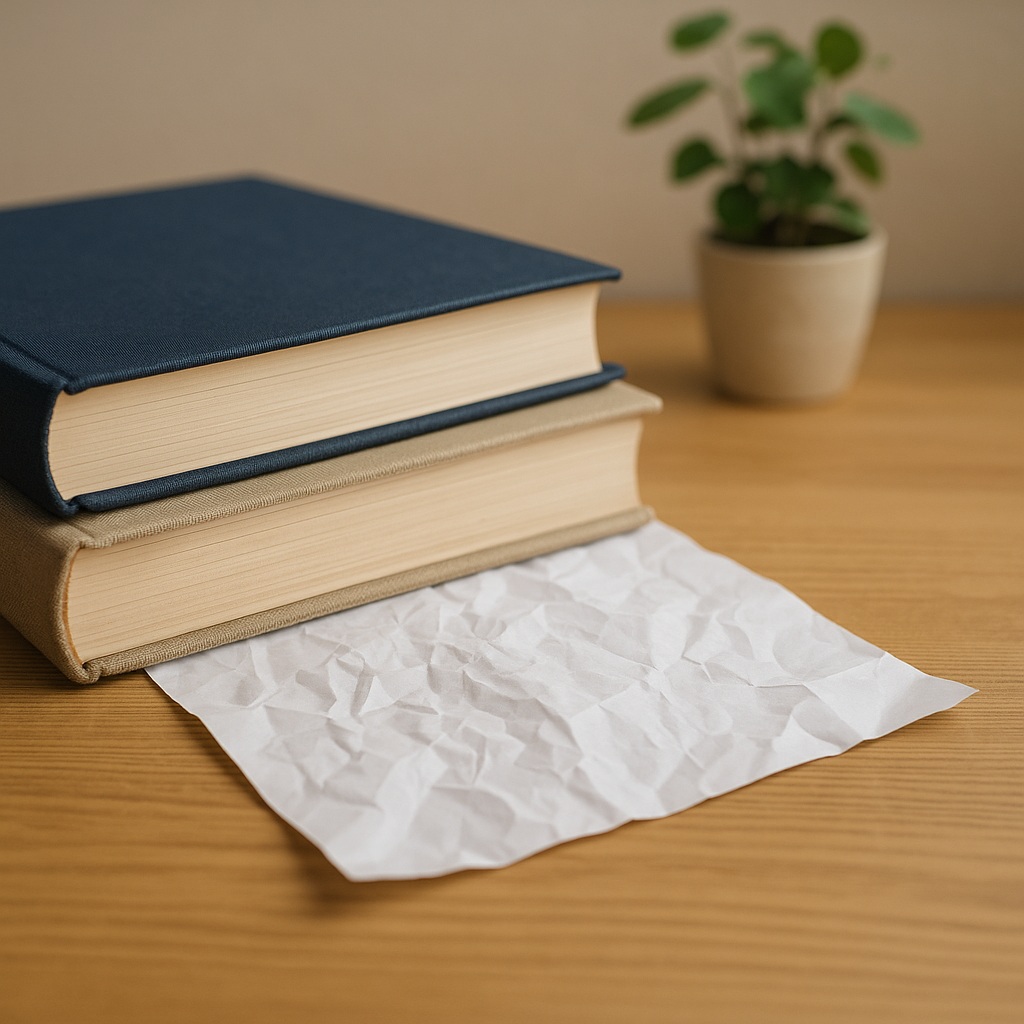
一度しわがついてしまった紙は、完全に元通りにするのはなかなか難しいものですが、見た目をぐっと整える方法はあります。
ここでは、時間をかけてじっくり直す方法から、短時間でしわを目立たなくするコツまで、幅広くご紹介します。
ぜひご自身に合った方法を見つけて、試してみてくださいね。
- 重しを使ったしわ取り法
- アイロンで簡単に伸ばす方法
- 湿らせてからアイロンをかける方法
- 冷凍庫を活用する裏ワザ
それでは、順番に詳しく見ていきましょう。
重しを使ってゆっくり整える方法
まずご紹介するのは、紙にやさしく、失敗の少ない重しを使った方法です。
紙に均等な重さをかけ、時間をかけて少しずつしわを伸ばしていきます。
時間はかかりますが、紙を傷めにくいのが大きな魅力です。
「大事な書類だから慎重にきれいにしたい」という方にぴったりの方法ですよ。
厚めの雑誌や板(2枚)
安定感のある重し(辞書や図鑑など)
必要に応じてスプレーボトル
手順
しわのある紙を、雑誌や板で上下から挟みます。
- その上に重しを置き、重さが均等にかかるように調整します。ペットボトルを使う場合は横に寝かせると安定します。
- このまま一晩から数日間放置します。
- 取り出して状態を確認し、しわが残っていれば紙を軽く湿らせて、もう一度同じ手順を試してみてください。
アイロンで手早く整える方法
次にご紹介するのは、時間がないときに便利なアイロンを使った方法です。
「紙にアイロンをかけるなんて大丈夫?」と思われるかもしれませんが、実は意外とよく使われているテクニックなんです。
紙は布ほど熱に弱くないので、温度と手順を守れば安心して使えます。
急いでしわを取りたいときにおすすめですよ。
アイロン
コピー用紙または薄手の布
手順
- アイロンの温度を低?中程度に設定します。
- 紙を直接アイロンに当てるのではなく、コピー用紙や薄い布で挟みます。
- 状態を見ながら、しわが取れるまでゆっくりとアイロンを当てます。必要に応じて、何度か繰り返してください。
水分をプラスして頑固なしわを整える方法
次にご紹介するのは、紙をほんのり湿らせてからアイロンを使う、少し応用的なしわ取りの方法です。
特に折れ目が強い部分や、深めのしわには効果的な方法ですよ。
「湿らせる」と聞くと紙が濡れすぎてしまうのでは…と心配されるかもしれませんが、使うのはごく少量の水分なのでご安心ください。
紙を傷めずに進められるのが、この方法の良いところです。
アイロン
しっかり絞った濡れタオル または 霧吹き
乾いた布やガーゼ
手順
- アイロンを低温?中温に設定します。
- 絞ったタオルで紙の表面を軽くポンポンと湿らせます。深いしわには霧吹きが便利です。
- 湿らせた紙を乾いた布やガーゼで優しく挟みます。
- アイロンを当てるときは、まず裏側からかけると安心です。
しわが目立たなくなるまで様子を見ながら繰り返します。必要に応じて、表と裏の両面にアイロンをかけて仕上げてくださいね。
冷凍庫を使った、ちょっと意外なしわ直しの方法
雨や湿気でふやけてしまった紙が、乾くとしわしわになって困った…そんなときに試せる、ちょっと意外な方法が冷凍庫を使ったしわ取りです。
この方法は、大きめの紙にはあまり向きませんが、ノートのページやメモ用紙のような小さめの紙なら、しっかり効果を発揮してくれます。
「ほかの方法ではうまくいかない」というときの、最後の手段として覚えておくと安心です。
ジッパー付き保存袋
必要に応じて霧吹き
手順
- しわのついた紙を保存袋に入れます。
- 袋の口は軽く閉める程度で構いません。
- 冷凍庫に立てた状態で入れ、24?48時間そのままにします。
取り出した後、紙に少し波打ちが残っているようなら、重しを使う方法を組み合わせると、よりきれいに整います。
紙のしわ取りで失敗しないために気をつけたい5つのポイント

紙のしわをきれいに直す方法はいろいろありますが、作業を進めるうえで意識しておきたい注意点もあります。
ちょっとした工夫を心がけるだけで、仕上がりがぐんと美しくなり、紙へのダメージも抑えることができますよ。
ここでは、特に覚えておきたい大切なポイントをご紹介します。
- 薄い紙やデリケートな紙は慎重に扱う
- 水を使う場合はインクや素材を確認する
- アイロンはスチームなしで使用する
- 熱を当てすぎないよう注意する
- ドライヤーの使用は避ける
では、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
① 薄い紙やデリケートな紙は優しく扱いましょう
半紙や和紙のような薄手の紙は、熱や冷凍の処理によって簡単に傷んでしまうことがあります。
また、レシートやATMの明細などに使われている感熱紙は、熱を加えると黒く変色してしまうので特に注意が必要です。
紙の種類によって、適したしわ取りの方法は異なります。
作業を始める前に、どんな紙を扱っているのかをよく確認しておきましょう。
② 文字や印刷された紙の水濡れに注意
白紙の紙であればあまり心配はありませんが、文字やイラストが印刷されている紙の場合は、インクの耐水性を事前に確認することが大切です。
水を使ったしわ取りは効果的ですが、水性インクが使われていると文字がにじんでしまうことがあります。
また、ポスターなど塗装された紙は、アイロンの熱で色落ちや変色が起こることもありますので、そんなときは布をかぶせ、裏面から優しくアイロンを当てると安心です。
③ アイロンのスチーム機能は使わないように
アイロンを使うとき、「スチームを使えば早くしわが取れそう」と思う方もいるかもしれません。
ですが、スチームを使うと紙が過度に湿ってしまい、逆に波打ったり扱いづらくなることがあります。
アイロンはドライ設定で使い、紙にはあらかじめ軽く水分を含ませる程度にとどめましょう。
④ アイロンは加熱しすぎないように
アイロンを長く当てすぎると、紙が黄ばんだり色あせたり、ひどい場合は焦げてしまうこともあります。
「もう十分しわが取れたかな」と感じたら、それ以上は無理にアイロンをかけずに終えるのが賢明です。
⑤ ドライヤーの使用は控えましょう
濡れた紙を早く乾かしたいとき、ついドライヤーを使いたくなることもありますよね。
ですが、ドライヤーの熱風は紙の水分を一気に飛ばしてしまい、乾いたときに波打ったような歪みができやすくなります。
紙をきれいに整えたいときは、ドライヤーを使わずに自然乾燥させるか、重しを使った方法を選ぶのがおすすめです。
しわのあるお札をきれいに整える方法
紙とひとことで言っても、コピー用紙、模造紙、厚紙など、種類はさまざまです。
しわ取りといえば、まずコピー用紙のことを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、意外と多いのが「しわの寄ったお札をきれいにしたい」というシーンです。
たとえば、お祝いの席で新札を準備し忘れてしまったとき、手元のお札をなんとか整えたいと思うこともありますよね。
実は、お札のしわも、一般的な紙と同じような方法である程度目立たなくすることができます。
もし、直接アイロンをかけるのに抵抗がある場合は、お札を軽く湿らせてから、本や板ではさみ、その上に重しをのせる方法がおすすめです。
時間はかかりますが、優しくしわを伸ばすことができますよ。
【紙のしわ対策まとめ】紙の種類に合わせたおすすめの方法
ここまで、紙のしわを整えるさまざまな方法をご紹介してきました。
中でも、最も安心して試せるのは、重しを使ってじっくりしわを伸ばす方法です。
また、アイロンを使う場合は、しわの深さや紙の素材に合わせて、使い方を調整することが大切です。
特に、水性インクが使われている書類や、繊細な紙の場合は、水分の量やアイロンの当て方に気をつけてくださいね。
アイロンを使う際は、スチーム機能はオフにし、低めの温度で短時間ずつ様子を見ながら進めるのがポイントです。
なお、ドライヤーを使ってしわを伸ばす方法は、紙を傷めたり、かえって状態を悪くすることがあるため、おすすめできません。
最後に、紙の種類やしわの程度によっては、完全に元通りにするのが難しい場合もあることを心に留めておきましょう。