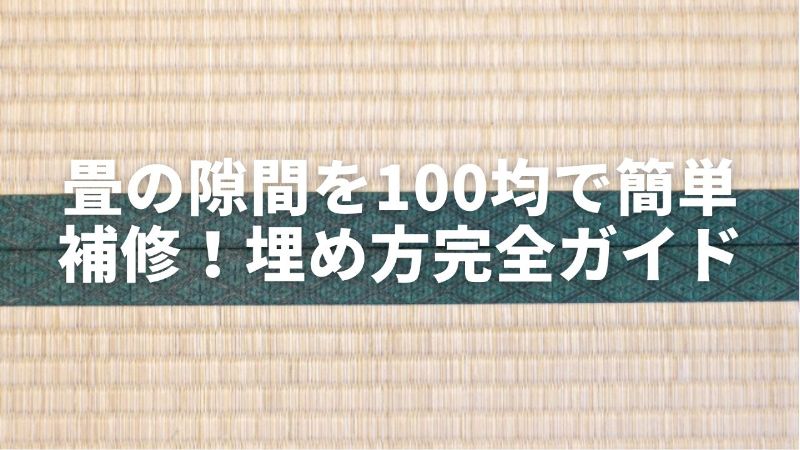畳の隙間が気になるけれど、「業者に頼むほどでもないし、自分で何とかしたい」と思ったことはありませんか。
実は、身近な100均アイテムを使えば、畳の隙間を手軽に補修できるんです。
隙間テープやスポンジ、パッキン材など、材料を上手に組み合わせることで、冷気やホコリを防ぎながら見た目も自然に仕上げられます。
しかも、どれも100円ショップで揃うのでコスパも抜群。
この記事では、初心者でも簡単にできる「畳の隙間埋め方」をステップごとに解説し、ダイソー・セリアのおすすめアイテムやプロのコツまで徹底紹介します。
和室の見た目を保ちつつ、快適に過ごしたい方はぜひ参考にしてみてください。
100均でできる!畳の隙間埋めの基本と選び方

畳の隙間は、時間の経過や湿度の変化で自然とできてしまうものです。
ここでは、100均アイテムを使って簡単に補修するための基本と、材料の選び方を解説します。
畳の隙間ができる原因とは?
畳の隙間は、主に湿気や乾燥による「畳の収縮」が原因です。
湿度が高い季節には膨張し、乾燥時期には縮むため、隙間が生じることがあります。
また、家具の重みや長年の使用による畳の変形も原因の一つです。
まずは原因を理解してから対策を選ぶのがポイントです。
| 原因 | 対策例 |
|---|---|
| 乾燥による収縮 | 隙間テープ・新聞紙で補填 |
| 家具の重み | クッション材を挟む |
| 経年劣化 | パッキン材や交換を検討 |
100均アイテムでできる隙間埋めのメリット
ホームセンターに行かなくても、100均アイテムを使えば手軽に隙間を埋めることができます。
コストを抑えつつ、見た目も自然に仕上がるのが魅力です。
特に賃貸住宅では、原状回復しやすいのが大きな利点です。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 低コスト | 材料費が100円〜で済む |
| 簡単施工 | 工具なしでも可能 |
| 取り外しやすい | 再施工がしやすい |
用途別に選ぶおすすめ素材と特徴
隙間の大きさや目的によって、使う素材を選ぶのがコツです。
例えば、冷気対策にはテープタイプ、見た目重視ならスポンジやモール材が適しています。
状況に合わせて複数の素材を組み合わせることで、より高い効果を得られます。
| 素材 | 特徴 | おすすめ用途 |
|---|---|---|
| 隙間テープ | 簡単に貼れる・気密性高い | 冷気・ホコリ防止 |
| スポンジ | 柔軟で加工しやすい | 広めの隙間対応 |
| 新聞紙 | 低コストで詰めやすい | 一時的な補修 |
| パッキン材 | 長期間使用に向く | 耐久性重視の補修 |
ダイソー・セリア別!隙間埋めに使えるおすすめアイテム

100均の中でも特に品揃えが豊富なダイソーとセリア。
ここでは、それぞれの店舗で手に入る畳の隙間埋めに使える便利アイテムを紹介します。
定番の隙間テープとその使い方
ダイソーやセリアの「隙間テープ」は、最も手軽で効果的な方法です。
テープ裏面の粘着部分をはがして、畳の隙間に沿って貼るだけでOKです。
クッション性のあるタイプを選べば、踏んでも沈みにくく快適に使えます。
貼る前に畳の表面をきれいに拭くことが、長持ちの秘訣です。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| ダイソー クッション隙間テープ | 厚みがあり、断熱効果も高い |
| セリア 防寒隙間テープ | 薄型で目立ちにくく貼りやすい |
スポンジ・パッキン・新聞紙の活用法
スポンジは自由にカットできるため、隙間の形状に合わせて使いやすいです。
発泡パッキンは軽量でしっかりした埋め効果があります。
新聞紙はコスパ最強で、一時的な補修には十分な効果を発揮します。
複数の素材を組み合わせて使うと、隙間の密閉性をさらに高められます。
| 素材 | 使い方 | ポイント |
|---|---|---|
| スポンジ | カットして隙間に詰める | 柔軟で再利用も可 |
| パッキン | 発泡素材で押し込む | 耐久性が高い |
| 新聞紙 | 細かくして隙間に押し込む | 低コスト・短期向け |
コーキング材やモール材の上級テクニック
隙間が広い場合や、より美しい仕上がりを求めるなら、コーキング材やモール材の使用がおすすめです。
コーキング材はシリコンタイプを選ぶと防湿性もあり、長期間安定します。
モール材は畳の色に合わせて選べば、自然な見た目で美しく隙間をカバーできます。
ただし、コーキング材は一度固まると取り外しにくいので、慎重に施工しましょう。
| アイテム | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| シリコンコーキング材 | 気密性が高く耐水性もある | 硬化後は再利用不可 |
| モール材 | 見た目が自然で和室になじむ | サイズ選びに注意 |
初心者でも簡単!100均でできる畳の隙間埋め手順

畳の隙間埋めは、専門的な技術がなくても100均アイテムを使えば簡単にできます。
ここでは、初心者でも安心して取り組める手順をステップごとに解説します。
準備する道具と材料リスト
まずは必要な道具をそろえましょう。
100均でほとんどが揃うので、特別な工具を買う必要はありません。
準備をしっかり行うことで、施工がスムーズに進みます。
| 道具 | 用途 |
|---|---|
| カッター・ハサミ | スポンジやテープをカット |
| 定規・メジャー | 隙間の幅を測る |
| 隙間テープ | 貼るだけで簡単に埋められる |
| 新聞紙・パッキン材 | 詰めるタイプの補修に使用 |
| コーキング材 | 広い隙間や湿気対策に使用 |
ステップごとの実践マニュアル
隙間埋めの流れを理解しておけば、初めてでも失敗しにくくなります。
以下の手順を参考に、丁寧に作業を進めましょう。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 畳表面を乾いた布で拭き、ホコリやゴミを除去 |
| 2 | 隙間の幅を測り、適した素材を選ぶ |
| 3 | 素材をカットして隙間に詰める、または貼る |
| 4 | 押し込みすぎず、畳の高さを揃えるように調整 |
| 5 | 仕上がりを確認し、浮きや段差がないかチェック |
隙間が広い場合は、テープとスポンジを併用すると密閉性がアップします。
作業中は畳を傷つけないよう、力加減に注意してください。
施工後に確認すべきポイント
施工が終わったら、見た目と効果をチェックしましょう。
もし隙間が再び開く場合は、詰めすぎや素材選びが原因かもしれません。
一度埋めたあとも定期的に点検することで、美しい状態を長く保てます。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 密着度 | 押してもぐらつかないか確認 |
| 見た目 | 色や素材が畳と馴染んでいるか |
| 耐久性 | 踏んだときに沈まないかチェック |
冷気・ホコリを防ぐ!100均の隙間テープ活用術

冬の寒い時期やホコリ対策にも、100均の隙間テープはとても役立ちます。
この章では、テープの種類や貼り方のコツを紹介します。
テープの種類と効果を比較
隙間テープには、スポンジタイプ・モヘアタイプ・ウレタンタイプなどがあります。
それぞれの特性を理解して使い分けることで、より高い効果を得られます。
| タイプ | 特徴 | おすすめ用途 |
|---|---|---|
| スポンジタイプ | 柔らかく加工しやすい | 畳の段差・隙間埋め |
| モヘアタイプ | 毛羽立ちがあり防音・防塵効果が高い | ドア下や窓際 |
| ウレタンタイプ | 密着性が高く長持ち | 冷気や虫の侵入防止 |
長持ちさせる貼り方のコツ
せっかく貼っても、すぐに剥がれてしまっては意味がありません。
長く効果を維持するには、下準備と貼り方が重要です。
貼る前に畳表面のホコリ・油分をしっかり落とすのが最大のコツです。
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. 表面を掃除 | 粘着力を保つために必須 |
| 2. 貼る位置を確認 | 一度貼ると剥がしにくいので慎重に |
| 3. 端を押しながら貼る | 空気が入らないようにする |
| 4. 仕上げに押さえつける | 粘着を安定させる |
冬におすすめの防寒シールの選び方
ダイソーやセリアには、冬の冷気対策にぴったりの防寒シールもあります。
畳の隙間や縁に貼ることで、冷たい空気の侵入を抑える効果があります。
透明タイプを選ぶと見た目が自然で、和室の雰囲気を損ないません。
| 商品名 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイソー 防寒隙間テープ | 厚みがあり冷気をしっかり遮断 | 110円 |
| セリア 透明防寒シール | 見た目がきれいで目立たない | 110円 |
| キャンドゥ すきま風防止パッド | 貼るだけで簡単施工 | 110円 |
冬の冷気対策としてだけでなく、夏場のエアコン効率アップにも役立ちます。
年間を通して使えるアイテムとして、一度貼っておくと快適さがぐんと上がります。
見た目もきれいに!和室になじむ素材選びのコツ

畳の隙間を埋めるとき、意外と気になるのが「見た目の仕上がり」です。
せっかく隙間を直しても、素材の色や質感が浮いてしまうと台無しですよね。
ここでは、和室の雰囲気を壊さずに自然に仕上げるための素材選びのポイントを紹介します。
ナチュラルカラーで統一する工夫
畳の色に近いナチュラルカラーを選ぶと、補修部分が目立ちにくくなります。
例えば、ベージュやモスグリーン、ブラウン系のパッキン材が相性抜群です。
色味をそろえるだけで、見た目の完成度がぐっと上がります。
| カラー | 特徴 | おすすめ用途 |
|---|---|---|
| ベージュ | 畳の自然な色合いに近い | 和室全般 |
| グリーン | 新しい畳との馴染みが良い | 新調した畳の補修 |
| ブラウン | 古い畳や縁部分に合いやすい | 年季の入った和室 |
畳の色に合わせた隙間パッキンの選び方
パッキン材を選ぶときは、畳のトーンに合わせるのがコツです。
明るめの畳には淡色パッキン、濃い色の畳にはダーク系パッキンを選びましょう。
店頭では実際に素材を畳にあてて確認するのがベストです。
| 畳の色味 | おすすめパッキン色 | ポイント |
|---|---|---|
| 明るい黄緑系 | アイボリー・ベージュ | 自然なトーンで溶け込む |
| 濃い緑系 | ダークブラウン・グレー | コントラストで引き締まる |
| 焦げ茶・古畳 | こげ茶・黒 | 経年劣化を目立たせない |
インテリアを損なわない隙間対策アイデア
隙間埋めを「デザインの一部」として活かすのもおすすめです。
たとえば、畳の縁に沿って木目調モール材を貼ると、まるで装飾のように見せられます。
“補修”を“アレンジ”に変えることで、より愛着のある空間にできます。
| アイデア | 使用素材 | 見た目の印象 |
|---|---|---|
| 木目調モール | セリアやダイソーのモール材 | 和モダン風のアクセント |
| 布テープ | 畳縁風のデザイン | 自然なつながりを演出 |
| 透明テープ | 見た目を崩さず補修可能 | ナチュラルで目立たない |
プロが教える!隙間をきれいに埋めるコツと注意点

DIYでの隙間埋めを成功させるには、プロの基本を押さえることが重要です。
ここでは、失敗を防ぎつつ長持ちする仕上がりを実現するためのコツを紹介します。
施工前に確認したい「隙間の原因」
隙間ができる原因を理解していないと、何度も再発してしまいます。
湿度・温度変化・家具の重みなど、原因に合わせた対策が必要です。
原因を無視した補修は、一時的にしか効果が続きません。
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 乾燥による収縮 | 季節に応じて隙間を調整できる素材を使用 |
| 湿気による膨張 | 通気性のあるテープや素材を選ぶ |
| 家具の重み | 下にクッション材を挟んで沈みを防止 |
失敗しやすい素材と避けるべき使い方
柔らかすぎる素材や、強力すぎる接着剤はトラブルのもとになります。
時間が経つと縮んだり、畳に跡が残ったりすることがあるため注意が必要です。
適度な弾力と剥がしやすさのバランスを意識して選びましょう。
| 避けるべき素材 | 理由 | 代替案 |
|---|---|---|
| 柔らかすぎるスポンジ | 時間とともに縮む | 発泡パッキン材 |
| 強力接着剤 | 畳を傷める可能性あり | 両面テープ・マスキング |
| 紙テープ | 耐久性が低い | ウレタン素材の隙間テープ |
長く保つためのメンテナンス方法
隙間埋めは一度やって終わりではありません。
季節や湿度によって畳の状態は変化するため、定期的な点検と微調整が必要です。
最低でも半年に一度は隙間の状態を確認しておくと安心です。
| メンテナンス時期 | チェック内容 | 対応策 |
|---|---|---|
| 春・秋 | 隙間の再発有無を確認 | 再度詰め直しや貼り直し |
| 梅雨前 | 湿気による膨張を確認 | 除湿剤を使用 |
| 冬前 | 冷気の侵入チェック | 防寒シールを追加 |
100均を活用した畳隙間埋めのまとめ
ここまで紹介してきたように、畳の隙間は100均アイテムを上手に活用することで、誰でも手軽に補修できます。
最後に、コスパ・見た目・耐久性の3つの視点から、最もバランスの取れた方法を振り返ってみましょう。
コスパ・見た目・耐久性のバランスを取るには
コスパだけを重視すると短期間で劣化し、耐久性ばかり追求すると見た目が悪くなることもあります。
「安く・きれいに・長持ち」する方法を意識するのが理想的です。
| 要素 | ポイント | おすすめアイテム |
|---|---|---|
| コスパ | 手軽で買い替えやすいものを選ぶ | 新聞紙・隙間テープ |
| 見た目 | 色や質感を畳に合わせる | モール材・ナチュラルカラーのパッキン |
| 耐久性 | 季節変化に強い素材を選ぶ | シリコンコーキング・発泡パッキン |
初心者でもできるおすすめ組み合わせ3選
どの素材を使えば良いか迷う人のために、初心者でも扱いやすい組み合わせを紹介します。
組み合わせることで、見た目と機能の両立ができます。
| 組み合わせ | 特徴 | おすすめシーン |
|---|---|---|
| 隙間テープ+スポンジ | 気密性が高く、柔軟に対応 | 冷気・ホコリ対策 |
| 新聞紙+マスキングテープ | 一時的な補修に最適 | 急な来客や応急処置 |
| パッキン材+モール材 | 長期間の補修に向く | 見た目を重視する和室 |
複数の素材を組み合わせることで、耐久性とデザイン性を両立できます。
今後のメンテナンスと再施工のタイミング
隙間を埋めたあとは、そのまま放置せず、季節ごとにチェックするのがおすすめです。
素材が縮んだり剥がれたりする前に、早めのメンテナンスを行いましょう。
半年〜1年に一度、隙間の状態を見直すだけで快適な和室を保てます。
| チェック時期 | 確認内容 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 春・秋 | 隙間の広がりや浮きを確認 | スポンジやテープの交換 |
| 梅雨前 | 湿気による膨張をチェック | 除湿剤を使用 |
| 冬前 | 冷気の侵入を確認 | 防寒シールを追加 |
畳の隙間は放置すると冷気やホコリの侵入だけでなく、ダニやカビの原因にもなります。
100均アイテムをうまく活用しながら、手軽で持続的な対策を心がけましょう。
「安く・簡単・きれい」を叶えるのが、100均DIYの最大の魅力です。