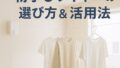法要や供養の際に欠かせない「塔婆(とうば)」。
いざ依頼しようと思っても、「どうやって申し込めばいいの?」「文面はどんなふうに書けばいいの?」と戸惑う方は多いものです。
この記事では、塔婆の意味や役割から、実際の依頼方法、すぐに使える例文、そして依頼時のマナーまでわかりやすく解説します。
初めての方でも安心して塔婆依頼ができるよう、ポイントを押さえておきましょう。
塔婆依頼の基礎知識
塔婆とは?意味と役割
塔婆は、故人やご先祖様を供養するために立てる細長い木の板で、一般的には杉や檜などの耐久性のある木材で作られます。
仏教の教えに基づき、表面には梵字や経文、裏面には故人の戒名や没年月日などが書かれます。
これを立てることによって、故人の冥福を祈り、善行を積むとされ、施主や遺族の供養の気持ちを形として表す役割があります。
また、塔婆はお墓の後方や墓石の横に立てられ、参拝者が故人を偲ぶ際の象徴ともなります。
塔婆が使われる場面と供養との関係
塔婆は、年忌法要・お盆・お彼岸・納骨式など、節目ごとの供養の場で立てられることが多いです。
宗派によって習慣や目的が少し異なり、真言宗では経文や梵字を重視し、曹洞宗では戒名や命日を中心に記載するなどの違いがありますが、共通して「追善供養(ついぜんくよう)」の意味を持ちます。
追善供養とは、生前にできなかった善行を後から補い、故人の成仏を願う行為であり、塔婆はそのための重要な供養具です。
塔婆の金額や一般的な相場
塔婆の費用は寺院や地域によって異なりますが、一般的には1本あたり3,000円〜5,000円程度が目安です。
寺院によっては長さや材質、記載内容によって金額が変わる場合があります。
依頼時には必ず事前に金額を確認し、法要当日または事前にお布施として「御塔婆料」の名目で包むのが礼儀とされています。
塔婆依頼の方法

申し込みの流れ(寺院・霊園の場合)
- 法要や納骨の日時が決まったら、できるだけ早めに寺院や霊園へ連絡します。このとき、日程の希望や法要の種類(例:一周忌、お彼岸法要など)も合わせて伝えるとスムーズです。
- 塔婆の本数・戒名・施主名・日付などの基本情報に加えて、必要があれば俗名や命日、宗派、特別な希望(大きさや形、記載内容など)も詳しく伝えます。誤記を防ぐため、口頭だけでなくメモやメールでの確認が望ましいです。
- 当日、お布施と一緒に依頼内容を再確認します。塔婆の設置場所や法要後の管理方法についてもこのときに確認しておくと安心です。
FAX・手紙・メールで依頼する場合
寺院によってはFAXや郵送、メールで依頼が可能です。この場合は「塔婆依頼書」や「申込用紙」に必要事項を記入し、期限までに送付します。
送付時には、戒名や日付に誤りがないか再度確認し、控えを手元に残すと安心です。
また、返信や受領確認の連絡があるかどうかも事前に確認しておきましょう。
宗派による依頼方法の違い
- 真言宗:梵字や経文を入れることが多く、寺院指定の書き方や様式に従う必要があります。依頼前に見本をもらい、記載漏れがないように準備しましょう。
- 曹洞宗:塔婆の形や記載内容はシンプルですが、戒名や俗名、命日などの記載順に細かい決まりがあるため、事前に寺院へ確認しておくことが大切です。
塔婆依頼の書き方と例文
基本的な塔婆依頼文例
拝啓 平素よりお世話になっております。日頃より何かとお力添えをいただき、心より感謝申し上げます。
来る○月○日(○曜日)○時より、○○寺にて○回忌法要を厳修いたします。
つきましては、故○○○○(戒名:○○○○)の塔婆を○本お願い申し上げます。塔婆の大きさや記載内容につきましては、御寺院のご指示に従います。
何卒よろしくお願い申し上げます。
施主 ○○○○
故人や法要の種類別の例文
- 一周忌の場合
○月○日の一周忌法要にあたり、故○○○○(戒名:○○○○)の塔婆を○本お願いいたします。当日は親族一同でお参りいたしますので、何卒よろしくお願いいたします。
- お盆の供養の場合
お盆の供養に際し、故○○○○(戒名:○○○○)の塔婆を○本お願い申し上げます。併せて、ご供養の際の留意点があればご教示ください。
- 十三回忌の場合
○月○日の十三回忌法要に伴い、塔婆を○本ご準備いただけますようお願い申し上げます。戒名や命日など詳細は別紙に記載しております。
お礼文や謝辞の書き方例
このたびは塔婆のご準備を賜り、誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。おかげさまで滞りなく法要を終えることができ、故人も喜んでいることと存じます。今後ともよろしくお願いいたします。
塔婆依頼のマナーと注意点

依頼時の基本マナー
- 法要の1〜2週間前には申し込む。可能であれば1か月前に目安を立て、寺院側と事前に打ち合わせしておくと安心です。
- 戒名や命日などの誤記を避けるため、必ず書面で確認する。口頭だけでなく、FAXやメール、申込書など記録が残る形で依頼し、控えを手元に保管しましょう。
- お布施は「御塔婆料」として包む。金額や包み方は地域や寺院によって異なるため、事前に確認することが望ましいです。また、熨斗や表書きの書き方にも注意しましょう。
- 当日は施主や代表者が直接寺院に挨拶し、法要前に再度依頼内容を確認するのが礼儀です。
地域や寺院による慣習の違い
地域によっては塔婆を親族全員が立てる習慣や、本数に決まりがある場合があります。
例えば、親や祖父母の法要では兄弟姉妹それぞれが1本ずつ立てる慣習や、奇数本を立てるのが良いとされる地域もあります。
寺院ごとに作法が異なるため、初めて依頼する場合は必ず事前に確認しましょう。
施主としての心構え
塔婆は「形式」ではなく「故人を思う気持ち」が大切です。
依頼時には丁寧な言葉と態度を心がけ、特に法要当日は慌ただしい中でも落ち着いた立ち居振る舞いを意識しましょう。
また、塔婆の意味や由来を理解して臨むことで、より気持ちのこもった供養となります。
依頼後の流れとよくある質問
依頼後に施主が準備しておくこと
- 塔婆料の用意。金額は事前に寺院へ確認し、御塔婆料として熨斗袋に包みます。
- 法要で塔婆を立てる位置の確認。お墓の正面か側面か、または既存の塔婆の配置との兼ね合いも考慮します。
- 焼香の順番や流れの把握。親族や参列者に事前に伝えておくことで当日の混乱を防げます。
- 供花やお供物、写真などの準備。法要の雰囲気を整え、故人を偲ぶ空間を演出します。
納骨や法要での塔婆の扱い
法要後は一定期間墓所に立て、その後寺院や霊園の指示に従って撤去します。
撤去後の塔婆はお焚き上げされる場合が多く、その際に追加の費用が発生することもあります。
地域や宗派によっては一定期間ごとに新しい塔婆へ交換する習慣もあるため、継続的な供養の計画を立てておくと安心です。
よくある疑問と回答
Q. 塔婆の本数は何本必要?
A. 施主1本のほか、親族がそれぞれ立てる場合もあります。また、特に親しい友人や縁の深い人が個別に塔婆を立てることもあります。寺院によっては法要の種類や規模に応じて本数の目安を案内してくれるため、事前に相談してみましょう。
まとめ
塔婆依頼は、事前準備と正確な情報の伝達が大切です。依頼内容や日時、塔婆の本数や戒名などの詳細をきちんと確認し、寺院や霊園とのやり取りをスムーズに行うことが、安心して供養を進めるための第一歩となります。
依頼文例を活用すれば、初めてでもスムーズに申し込むことができ、言葉遣いや形式で迷う心配も減ります。
さらに、文例をもとに自分なりの感謝や想いを添えることで、より心のこもった依頼となります。
故人を偲ぶ気持ちを込めて、心を尽くした供養を行いましょう。
その時間や手間は、必ずや遺族や参列者の心を温め、故人への想いを深める大切な機会となるはずです。