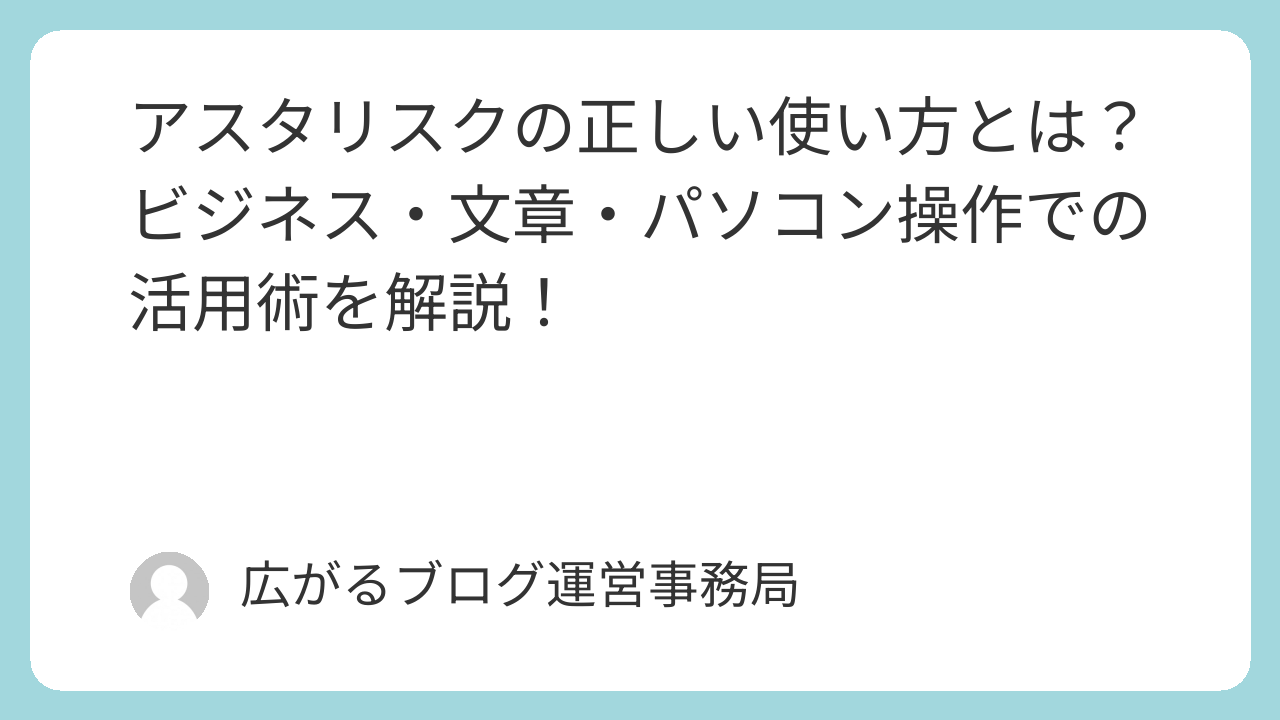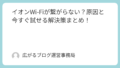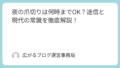アスタリスクの正しい使い方とは?ビジネス・文章・パソコン操作での活用術を解説!
はじめに|アスタリスク、ちゃんと使えてる?
「*」このマーク、見たことはあるけど…どうやって使うのが正解?
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
アスタリスクは、文章の補足説明や検索、さらにはビジネス文書まで、実はかなり幅広く使える記号です。ただし、使い方を間違えると相手に伝わりづらかったり、ちょっとマナー違反になったりすることも。
この記事では、アスタリスクの意味から実践的な使い方、そして注意点までをわかりやすく解説していきます。「あ、そういう使い方だったのか!」とスッキリできるはずなので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね😊
アスタリスクとは?基本の意味と用途
アスタリスクの記号の由来と意味
アスタリスク(*)は「星印」とも呼ばれ、その名の通り小さな星のような形をしています。見た目は単純ですが、実は非常に古くから使われてきた歴史ある記号です。語源はギリシャ語の「asteriskos(小さな星)」に由来し、古代の写本などでも補足や修正を示すマークとして使われていたことが確認されています。
この記号は、英語圏では特に注釈をつけるためや、省略された情報を示すために活用され、日常の文書から学術論文、コンピュータの検索操作など、さまざまな分野で広く用いられています。また、近年ではSNSやチャットツールなどでも使われるようになり、カジュアルな場面でも見かけることが多くなってきました。
その柔軟な使い道と、場面に応じて意味が変わる特性から、アスタリスクは「多機能記号」とも言える存在です。
星印や米印との違いは?
アスタリスクとよく混同されがちなのが「※(米印)」です。これらは一見似ているようでいて、使われる場面や意味が大きく異なります。
- アスタリスク:* ← 主に英語圏で使用され、注釈や検索のワイルドカードなどに使われる
- 米印:※ ← 日本語の文書に多く登場し、注意書きや補足情報に用いられる
たとえば、ビジネス文書や公的な案内文では「※ご注意ください」といった形で米印が使われることが一般的です。一方、英語ベースの資料やIT系のマニュアルではアスタリスクが頻繁に登場します。
使い方が似ているため、なんとなく交互に使ってしまいがちですが、見ている相手や使用シーンを考慮して、正しく使い分けることが大切です。
シーン別アスタリスクの使い方
文章中での使い方(補足・注釈など)
文章の中で補足説明を入れたいときに、アスタリスクを使って注釈を示すことができます。特に、難しい専門用語や例外事項などを補足したいときに便利です。読者の理解を助けるために、本文中に直接書ききれない情報を補足する際の定番手法です。
たとえば、文中に「この製品は*1日1回の使用を推奨しています。」と記載した後、本文の末尾や脚注部分で「*1 使用上の注意を参照」と詳しく説明を加えることで、読者にとって親切で分かりやすい文章に仕上がります。
また、論文やレポートなどでも注釈番号の代わりにアスタリスクを使う場合があり、視認性の高さから読みやすさにも貢献します。特に紙面のスペースが限られている場合、コンパクトに補足できる点がメリットです。
使い方としては、1つ目の補足には「」、2つ目には「」、3つ目には「」と段階的に増やしていく方法もあり、複数の注釈を並べたいときにも活用できます。
ビジネス文書・資料での活用方法
ビジネス文書では、項目の強調や注記の目印として使われることが多いです。たとえば、契約書や会議資料で「*重要」などのように使えば、見る人にとって視認性が上がり、意識してほしいポイントを的確に伝えることができます。
また、商品の仕様書やマニュアルなどで「*印は推奨事項です」など、記号に意味を持たせることもできます。ただし、複数の記号を並べて使うと読みにくくなるので、1~2個までがベストです。
さらに、アスタリスクの意味や用途を明記しておくと、受け取った相手も混乱せずに理解しやすくなります。社内外問わず、共通のルールを設けておくとより効果的です。
パソコン・スマホでの入力方法
- Windows:Shift + 8 を同時に押すと、アスタリスク(*)が入力できます。基本的にどのアプリケーションでも共通で使えるので、メモ帳やWord、Excel、ブラウザの検索窓など、幅広い場面で入力可能です。また、日本語入力モードになっている場合は、意図せず別の記号に変換されることもあるので、英字モードで入力するとスムーズです。
- Mac:こちらも同様に Shift + 8 でアスタリスクを入力できます。Macの英語キーボード、日本語キーボードどちらでも位置は変わらないため、すぐに慣れることができます。また、Macではショートカットやスニペット機能を使って、頻出記号として簡単に呼び出す設定も可能です。
- スマホ:iPhoneやAndroidのスマートフォンでは、キーボードを表示させた後、「123」や「#+=」といった記号入力用のボタンをタップして、記号一覧に切り替えるとアスタリスクが表示されます。端末やキーボードアプリによって配置が異なることもあるため、よく使う記号は「お気に入り」や「ユーザー辞書」に登録しておくと便利です。
このように、パソコンでもスマホでも比較的簡単に入力できるアスタリスク。特に難しい操作はないので、日常的に気軽に使えます◎
意外と知らないアスタリスクの便利技
Google検索での使い方
アスタリスクはGoogle検索でも大活躍!
検索演算子として使われ、ワイルドカード(なんでも当てはまる単語)の役割を果たします。つまり、検索したいキーワードの一部が思い出せないときや、前後に入る単語を幅広く検索したいときに非常に便利です。
例えば、「* 方法」と検索すると、「簡単な方法」「効果的な方法」「最新の方法」など、の部分にあらゆる言葉が入った検索結果が表示されます。また、「料理の」といった形で使えば、「料理のコツ」「料理の基本」「料理のコース」などもヒットします。
この使い方は、アイデア出しやリサーチ、記事タイトルのインスピレーション収集にも活用可能です。特にSEOライターやブロガーにとっては重宝するテクニックといえるでしょう。ちなみに、アスタリスクは単語の途中では使えず、基本的には単語の前後に使用することが推奨されています。
エクセルやワードでの活用術
- Excel:検索や置換機能で「」を使えば、任意の文字列を一括で処理できます。たとえば、「AZ」と入力すると、「A」で始まり「Z」で終わるすべての文字列が対象になります。また、「*」と「?」を組み合わせることで、さらに柔軟な検索が可能です。
- Word:同じく「検索と置換」で、「*」を使って任意の語句をまとめて見つけることができます。大量のテキスト処理や編集作業において、このワイルドカード機能は大きな助けになります。
地味に感じるかもしれませんが、こうした小さな効率化が、資料作成や編集作業の生産性を大きく左右します。慣れると手放せないテクニックになりますよ!
SNSやチャットでの注意点
SNSやチャットアプリでは、アスタリスクが「強調」を意味するケースもあります。たとえば「重要」と書くと、海外のフォーマットでは「重要」という単語が太字で表示されることがあります。
ただし、日本語環境では太字にはならず、*マークだけがそのまま表示されてしまい、「なにこれ?」と誤解されることも。さらに、文脈によっては強調のつもりが逆に読みにくくなる場合もあります。
また、SlackやDiscordなど一部のチャットツールでは、アスタリスクを使ったMarkdown記法が対応しており、太字・斜体などのスタイル変更が可能です。ツールごとのルールを理解して使い分けるのがポイントです。
アスタリスクを使うときの注意点とマナー
使いすぎはNG?読み手に配慮した使い方
アスタリスクはとても便利な記号ですが、使いすぎると逆効果になることもあります。あまりにも多用すると、文章がゴチャゴチャして視認性が下がり、読み手が混乱する原因になります。特に、補足説明や強調のつもりで頻繁に使ってしまうと、かえって本当に伝えたい内容の印象が薄くなってしまうのです。
たとえば、ひとつの段落の中にアスタリスクが何度も出てくると、注釈の意味がかえって分かりにくくなります。読み手は「これは重要?補足?装飾?」と迷ってしまい、結果として伝えたい情報がぼやけてしまうことになります。そうならないためにも、アスタリスクは本当に伝えたい箇所だけに絞って使うのがベストです。
また、文章全体のトーンやバランスも意識しましょう。たとえば、論文やビジネス文書のようなフォーマルな場面では、アスタリスクの使いすぎは軽い印象を与えることもあります。読み手の立場に立って、「ここにアスタリスクがあると読みやすくなるかな?」と一度立ち止まって考える姿勢が大切です。
ビジネスシーンでの注意点
ビジネス文書では「※」のほうが正式感があるとされることも。たとえば契約書や報告書などでは、アスタリスクよりも米印(※)を使う方が丁寧な印象を与える場合があります。
特に目上の方や社外の相手に向けた文書では、記号の選び方ひとつでも信頼感や印象に差が出るため、相手や場面に応じて記号を適切に使い分けることが求められます。また、社内ルールやテンプレートに記号の使用法が決まっているケースもあるので、それに従うのがベターです。
混同しやすい記号との違いを再確認
アスタリスク(*)と、ハイフン(-)、ダッシュ(—)、中点(・)などは、見た目が似ていて誤解されやすいので要注意です。それぞれに異なる意味や役割があるため、混同すると誤解を招く可能性があります。
たとえば、「・」はリストの区切りや並列関係を示す記号であり、「-」は単語のつなぎや範囲を表す記号です。「—」は文章内の間を作る装飾的な使い方がされますが、これもアスタリスクと一緒に使うと視覚的にごちゃついてしまう原因になります。
特に文章作成ソフトやデザインソフトでは、記号ごとに異なるフォント幅やスタイルが適用されることもあり、見た目が不揃いになりがちです。文章をすっきりと整えるためにも、記号の使い分けには注意が必要です。
まとめ|アスタリスクを正しく使えば、伝わり方が変わる!
アスタリスクは、注釈や検索、資料作成などあらゆる場面で役立つ記号です。
でも、便利な一方で使いすぎたり誤解を招いたりすることもあるので、使いどころとマナーを意識することが大事です。
「ただの飾り記号」と思っていたアスタリスクが、今ではちょっと頼もしく見えてきませんか?
この記事があなたの疑問解消に役立てばうれしいです😊