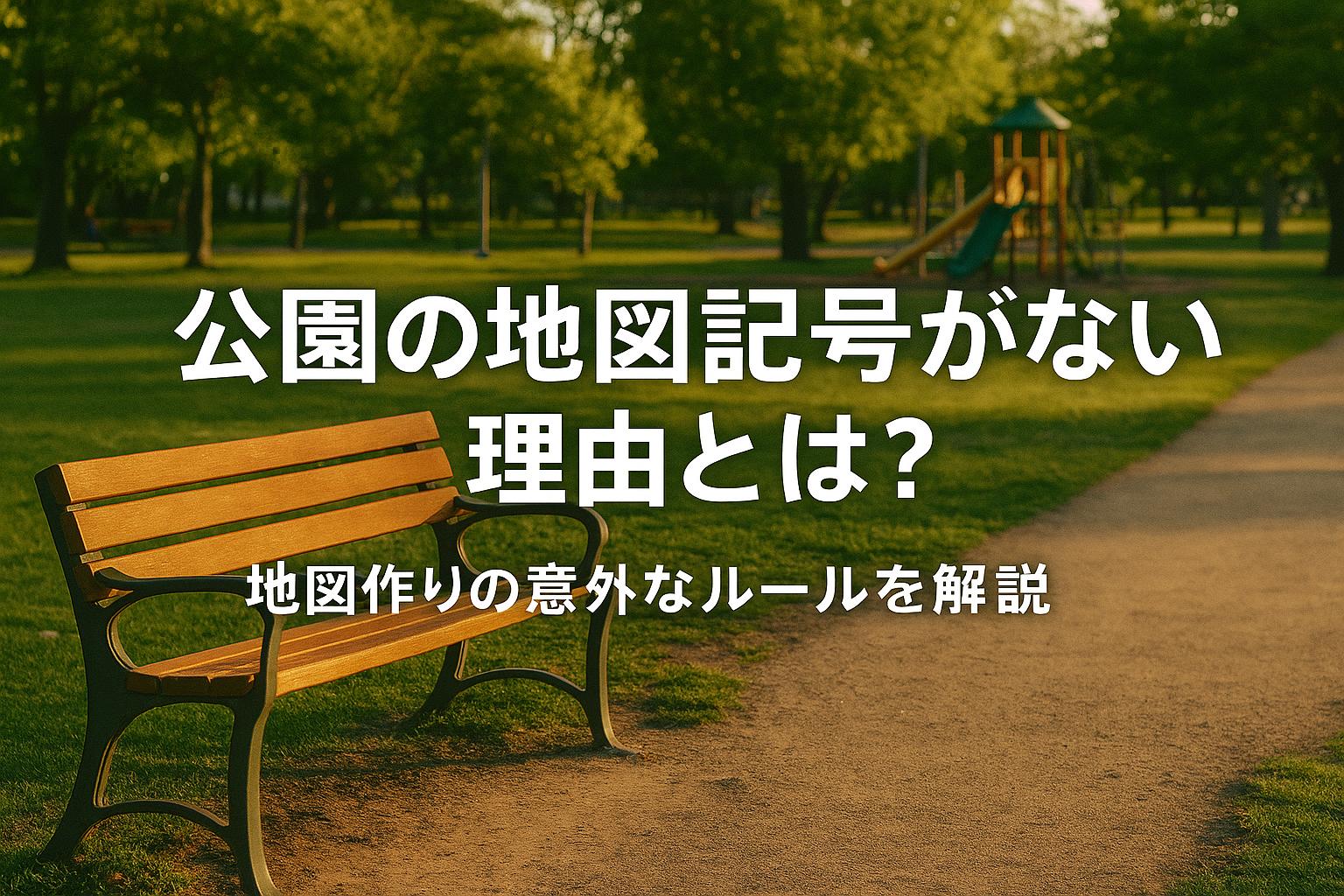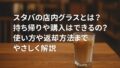「地図に公園の記号ってなかったっけ?」と思ったことある方も多いのではないでしょうか?でも実は、公園には正式な”地図記号”は存在しないんです。その理由は、地図の作り方に定められた約束や、公園という場所が素晴らしくも常に多様で、個所によって種類や性質が大きく異なるからです。ひと言で「公園」と言っても、こども用の遊具がある場所もあれば、自然貴重な林のような美しい総合公園もあります。そのため、簡単な記号で一般化するのが難しいのです。この記事では、公園に地図記号がない理由に続き、実際に地図上でどのように公園を見分けることができるのか、やさしくわかりやすく解説していきます!
公園に地図記号がないって本当?

公園にもマークがあると思っていたけど?
多くの人は、地図上で見かける木のマークやベンチのイラストを見て、「これが公園の地図記号だ」と思い込んでしまいがちです。しかし、実はこれらは正式な地図記号ではないんです。こうしたマークは、地図をよりわかりやすくするために作られた案内用記号やピクトグラムと呼ばれるもので、用途や地図の種類によってデザインも自由にアレンジされています。特に観光地図などでは、親しみやすさを重視して可愛らしいデザインになっていることも多く、正式な地図記号とは別物と考えたほうが良いでしょう。
そもそも「地図記号」とは何か
地図記号とは、国土地理院などの公的機関によって定められた、地図上で情報を共通して表現するためのマークのことを指します。これらは全国どこでも同じ意味を持つように統一され、誰が見てもすぐに理解できるように設計されています。例えば、学校は「文」の字を模したマーク、警察署は盾をイメージしたマークなどが代表例です。地図記号は、明確な定義とルールに基づいて使用されているため、場所によって形や意味が変わることはありません。
「公園マーク」と「地図記号」の違い
案内用マークは、見る人に直感的に意味が伝わるように作られているため、自由度が高く、デザイン性も重視されています。地図制作者の意図や利用者のニーズに応じて、形や色、スタイルが大きく変わるのが特徴です。一方で地図記号は、厳格なルールのもとで統一されており、自由にデザインを変更することはできません。このため、公園のマークも、案内用記号としてはさまざまなバリエーションが存在するものの、地図記号として正式に定められたものはないのです。
なぜ公園には正式な地図記号が存在しないのか
地図記号の制定ルール
地図記号は、全国どこでも共通に使える必要があるため、誰が見てもすぐに理解できるシンプルさと統一性が求められます。そのため、場所ごとに形や用途が大きく異なる対象物は、統一された記号にまとめにくく、記号化が見送られる傾向にあります。また、地図記号に採用されるためには、社会的に広く認知されている施設や自然物であることも重要な条件となっています。地図を使う人に混乱を与えず、一定の情報量を簡潔に伝えるための厳しい基準があるのです。
公園の多様性が影響している
「公園」とひと口に言っても、その実態は非常に多様です。小さな児童公園から大規模な運動公園、さらに国立公園のような広大な自然公園まで、規模や目的、施設の内容は千差万別です。遊具が中心の公園もあれば、森林浴を楽しむための自然保護型の公園もあります。これほど種類が豊富な公園を、ひとつのシンプルな記号で表現するのは現実的に難しく、結果として正式な地図記号は制定されていないのです。
公園マークは案内用記号に分類される
このため、地図上では公園を示す際に案内用記号やピクトグラムが使われることが一般的になっています。これらは、直感的に内容を伝えることを重視して作られているため、地図制作者の意図やデザイン方針に応じてさまざまなバリエーションが存在します。緑地の色分けや、樹木のイラスト、ベンチのシンボルなどが公園の存在を示す手段として使われることが多く、利用者にわかりやすい表現を優先した結果といえるでしょう。
地図で公園をどう見分ける?実際の見方を紹介

公園は色や表示で区別される
都市地図では、公園は緑色の塗りつぶしや斜線で示されることが多く、誰でもパッと見ただけで公園や緑地だとわかるような工夫がされています。また、地図によっては色の濃淡やパターンの違いで、自然公園や都市型公園などをさらに細かく区別している場合もあります。これらの色分けは、地図を読む上でとても重要な手がかりになるため、ぜひ注目して見てみましょう。
地図の種類(都市地図・観光地図)による違い
地図にはさまざまな種類があり、それによって公園の表現方法も変わります。都市地図ではシンプルに色や斜線で表されることが多いですが、観光地図ではより視覚的にわかりやすくするために、イラスト付きの公園マークやピクトグラムが使われることがよくあります。ただし、こうしたイラストは正式な地図記号ではなく、あくまで案内用に作られたものである点に注意が必要です。
覚えておきたい!代表的な地図表現例
- 緑色のエリア:公園や緑地、自然保護区などを示す。
- ピクトグラム:施設案内用に使われる直感的なマーク(遊具やベンチのイラストなど)。
- 標高線:地形の高低差を示す線で、公園の中にある丘や谷の存在を把握できる。
- 道の記号:道路や小道を示す記号で、公園内の散策路やアクセスルートを確認できる。
こうした複数の情報を組み合わせて読むことで、公園の規模や特徴、さらには周辺施設との位置関係までより正確に把握できるようになります。地図を見る際には、単なる色やマークだけでなく、周囲の地形や施設表示にも目を向けると理解が深まりますよ。
公園マークと地図記号を混同しやすいケース
案内図や観光マップでよく使われるマーク
観光地では、公園や遊び場を目立たせるために、独自のデザインで作られた案内用マークが頻繁に使われています。たとえば、かわいい木のイラストやベンチ、噴水、子供たちが遊ぶ姿を象ったマークなど、見た目に楽しく親しみやすいデザインが施されていることが多いです。こうしたマークは視覚的に非常にわかりやすいため、多くの人が「これが正式な地図記号なのだ」と誤解してしまう原因となっています。しかし、これらはあくまでも案内用であり、地図記号とは異なる扱いになります。
誰もが一度は混乱する?似ている記号たち
地図を見ていると、ベンチのマークや大きな樹木のイラスト、さらには芝生エリアを示す図案など、さまざまな似たような記号が登場します。特に観光地やテーマパーク周辺の案内図では、デザインにバリエーションがありすぎて、何を指しているのか混乱してしまうこともしばしばです。しかし、これらは正式な地図記号ではなく、作成者の意図によってアレンジされた案内記号なので、公式地図記号とは明確に区別して理解する必要があります。
地図記号と案内記号の見分けポイント
地図記号は、国土地理院などの公的機関が厳密なルールに基づいて制定した統一されたシンボルです。形、意味、使用方法に至るまで厳格に管理されており、全国どこでも共通して使用されます。一方、案内記号は自由度が高く、地図の目的や利用者層に合わせて柔軟にデザインされるため、制作者によってバリエーションが豊富です。見た目の可愛らしさや直感的なわかりやすさを重視して作られることが多いのが特徴です。これらの違いを意識して地図を見ると、より正確に情報を読み取れるようになりますよ。
まとめ:公園の「マーク」はあるけど「地図記号」とは違う
地図上で公園はよく目にしますが、正式な地図記号は実は存在しないのです。その理由は、公園の種類が非常に多様であり、ひとつの統一された記号で表現することが難しいためです。現在、公園は案内用記号や色分けを使って柔軟に表現されています。地図を見るときには、地図記号と案内記号の違いをしっかり意識することで、より正確に情報を読み取り、地図を活用できるようになりますよ!