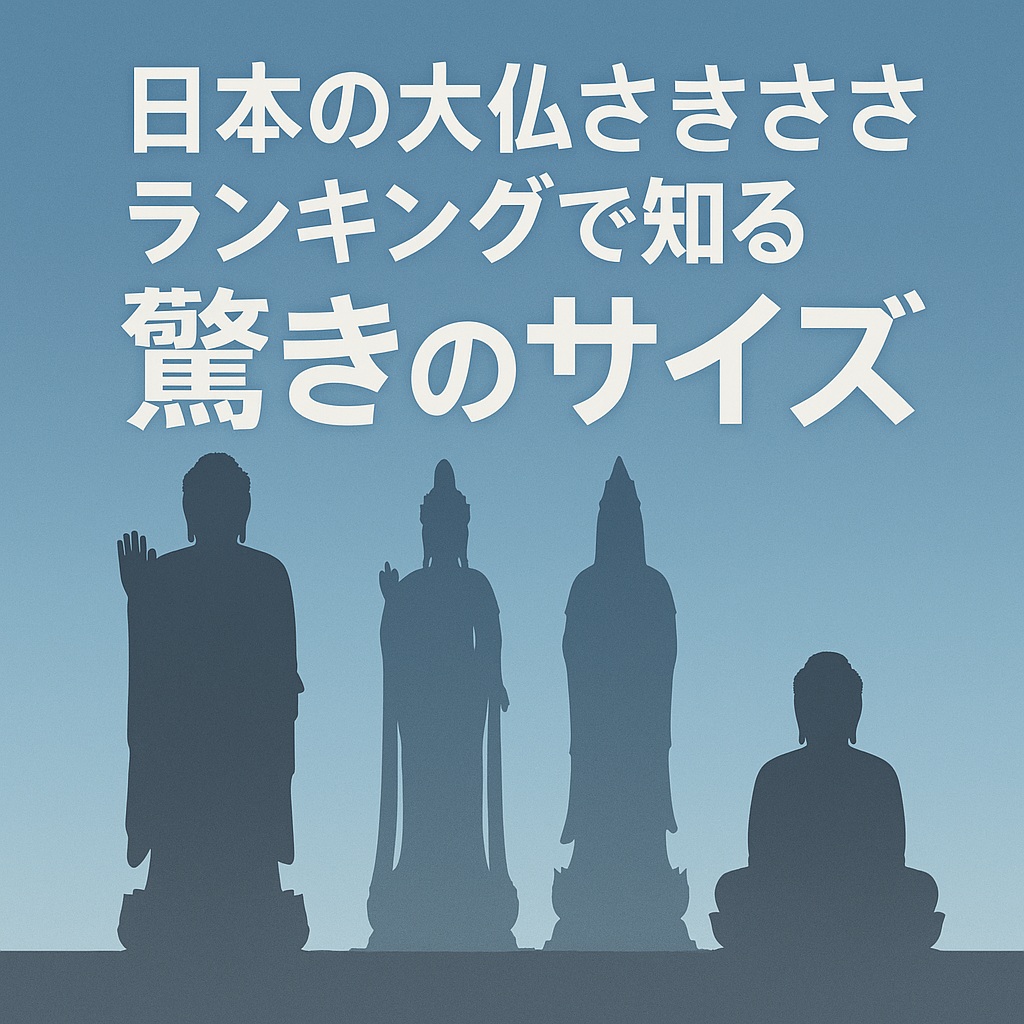「大仏」と聞いて、あなたはどの仏像を思い浮かべますか?
奈良の大仏、鎌倉の大仏…有名どころはもちろんですが、日本には驚くほど巨大な仏像がたくさんあるんです。
実は“日本一大きい大仏”は奈良ではなく、茨城県にある牛久大仏。その高さなんと120メートル!
この記事では、日本全国にある代表的な大仏のサイズをランキング形式で紹介しながら、それぞれの見どころや歴史的背景もわかりやすく解説していきます。
日本の大仏大きさランキング(高さ一覧)
ランキング表で一目瞭然!日本各地の巨大仏像
| 順位 | 大仏名 | 所在地 | 高さ(m) | 建立年 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 牛久大仏 | 茨城県 | 120 | 1993年 |
| 2位 | 仙台大観音 | 宮城県 | 100 | 1991年 |
| 3位 | 北海道天徳大観音 | 北海道 | 88 | 1989年 |
| 4位 | 東京湾観音 | 千葉県 | 56 | 1961年 |
| 5位 | 鎌ケ谷大仏 | 千葉県 | 45 | 1776年 |
| 6位 | 高崎白衣大観音 | 群馬県 | 41.8 | 1936年 |
| – | 奈良の大仏 | 奈良県 | 15 | 752年 |
| – | 鎌倉大仏 | 神奈川県 | 13.35 | 1252年 |
※建設年はおおよその完成年を示しています
大仏の特徴と見どころ

胎内めぐりで体験する牛久大仏
世界最大級の大仏としてギネスにも認定された牛久大仏は、全高120メートルを誇り、その圧倒的な存在感で訪れる人々を魅了しています。
特に特徴的なのが、胎内に入って見学ができる点。エレベーターで上層部まで上がると、窓からの眺望や、巨大な仏像内部ならではの静謐な空間が広がります。
内部には、地獄と極楽をテーマにした展示コーナーや、写経体験、仏教美術の展示などもあり、学びと癒やしの両方が味わえる貴重なスポットとなっています。
光が差し込む広間では、心を落ち着けて瞑想できる空間も用意されており、精神的なリトリートとして訪れる人も多いのが特徴です。
奈良の盧舎那仏とは?
奈良の大仏は、“盧舎那仏(るしゃなぶつ)”と呼ばれ、東大寺の本尊として752年に開眼された、歴史的にも文化的にも極めて重要な存在です。
高さは約15メートルで、現代の巨大仏像と比較するとコンパクトに見えるかもしれませんが、当時の技術力でこれほどの大仏を建立したこと自体が奇跡ともいえる偉業です。
さらに、仏像の制作や修復に関わった人々の記録が残っており、歴史の生き証人ともいえる存在です。周囲を囲む荘厳な建築とともに、訪れる人に深い感動を与えています。
鎌倉大仏のユニークな魅力
鎌倉大仏は、神奈川県鎌倉市の高徳院にある青銅製の阿弥陀如来坐像で、建長5年(1252年)頃に造立されました。
高さは約13.35メートルとそこまで大きくはないものの、凛とした表情と屋外に鎮座するスタイルが非常に印象的です。
かつては立派な大仏殿に覆われていましたが、15世紀の津波で失われてからは、現在のように青空の下で親しまれています。
内部に入ると、厚さ約30cmの青銅の壁を間近で見ることができ、その造形の細かさや当時の鋳造技術の高さに驚かされます。
街中にありながらも、心を穏やかにしてくれる空間として、地元の人々からも長く愛され続けています。
仏像の意味と豆知識
観音菩薩と阿弥陀如来の違い
仏像には実に多様な種類が存在しており、それぞれが異なる役割や意味を持っています。
中でも観音菩薩と阿弥陀如来は、日本でも特に多く見られる代表的な仏像です。
観音菩薩は「慈悲」の象徴として、困っている人や悩みを抱える人々を優しく救ってくれる存在とされています。姿かたちも多彩で、千手観音や十一面観音など、バリエーションが豊富なのも特徴です。
一方の阿弥陀如来は、「智慧と救済」を象徴する仏で、死後に極楽浄土へ導いてくれると信じられています。特に浄土宗や浄土真宗では阿弥陀如来への信仰が深く、手を合わせることで安心感や心の平穏を得る人も多いです。
大仏にもそれぞれ異なる仏がモデルとなっており、たとえば牛久大仏は阿弥陀如来、奈良の大仏は盧舎那仏、鎌倉大仏は阿弥陀如来とされています。
参拝の際に仏像の名前や特徴を知っておくと、見方がより深まり、仏像鑑賞の楽しみが一層広がります。
実は世界最大⁉日本の仏像の存在感
牛久大仏は、全高120メートルという規格外の高さを誇り、なんと自由の女神(約93メートル)よりも高いことで有名です。
そのスケールの大きさから、海外の観光客も多く訪れ、近年では“世界でも有数の巨大仏像”としてメディアでも取り上げられています。
この牛久大仏は、最新の建築技術と日本古来の仏教文化が融合した建造物ともいえ、その内部構造や設計にも多くの工夫が凝らされています。たとえば、内部の展示はテーマ別に分かれており、仏教の教えを視覚的に学べるようになっていたり、上層階からは茨城の景色が一望できる設計になっていたりと、ただの仏像にとどまらない魅力があります。
日本の大仏は、単なる観光資源にとどまらず、信仰の対象として、そして文化や建築の象徴として、今なお人々の心を惹きつけ続けているのです。
まだまだある!地方のユニークな大仏
仙台・加賀・兵庫の大仏たち

仙台の大観音像は、真っ白な外観と近未来的なフォルムが特徴で、遠くからでもひときわ目を引く存在です。高さは100メートルにも及び、内部には螺旋階段や仏教の教えを紹介する展示スペースが設けられ、仏像としてだけでなく文化体験の場にもなっています。
加賀大観音(石川県)は、観音像の中でも比較的知名度が低いながらも、その荘厳な姿と静寂な雰囲気が魅力。山間に位置しているため、周囲の自然との調和も美しく、心が洗われるような体験ができます。現在は内部公開が制限されていることもあるので、事前の調査が必要ですが、その神秘性がかえって訪れる価値を高めています。
兵庫の川西大仏は、高さはそれほど大きくはないものの、地域密着型の大仏として住民に愛されています。四季折々の花に囲まれた境内では、春の桜や秋の紅葉とのコラボレーションが写真映えするスポットとしても人気です。都市部からのアクセスもよく、週末のお出かけ先としてもおすすめです。
穴場スポットとしての地方大仏
こうした地方の大仏は、有名観光地のように混雑していないため、ゆっくりとした時間の中で参拝できるのが大きな魅力です。
歴史の重みを感じながら、静かに手を合わせることで、自分自身と向き合うひとときにもなります。
さらに、最近ではSNSやインスタグラムの影響で、ユニークなフォルムや自然とのコントラストが映える大仏は“映えスポット”として若者たちにも人気が高まっています。
あまり知られていない分、自分だけの穴場を見つけたような喜びもあり、仏像ファン以外の層からも注目を集めつつあるのが現状です。
地方の大仏めぐりは、観光と癒しの両方を味わえる新しい旅のスタイルとして、今後ますます注目されることでしょう。
まとめ
日本には、サイズも歴史もさまざまな大仏が存在します。単に「大きい順」で見るだけでなく、仏像が建てられた時代背景や、地域ごとの信仰、そして人々の想いを知ることで、その魅力は何倍にも膨らみます。
実際に足を運んでみると、写真では伝わらない迫力や、周囲の風景との調和、静けさの中に宿る神聖さなど、心に深く残る体験ができます。この記事をきっかけに、自分だけの“大仏お気に入りリスト”を作って、大仏めぐりの旅に出てみてはいかがでしょうか?