「動物のIQ」と聞くと、イルカやチンパンジーのような賢い動物を思い浮かべる人も多いでしょう。
でもその逆、IQがかなり低いとされる動物たちも実はたくさん存在しています。中には「本当に生きていけるの?」と思ってしまうほど、シンプルな行動パターンしか持たない動物も。
とはいえ、知能の高さ=優れているという単純な考えでは語れないのが動物の世界。
この記事では、そんな“低IQ動物”たちの驚きの特徴を、ランキング形式で楽しく紹介していきます。
また、IQの定義や誤解されがちなポイントについても、わかりやすく解説していきます!
IQとは?動物における知能の考え方
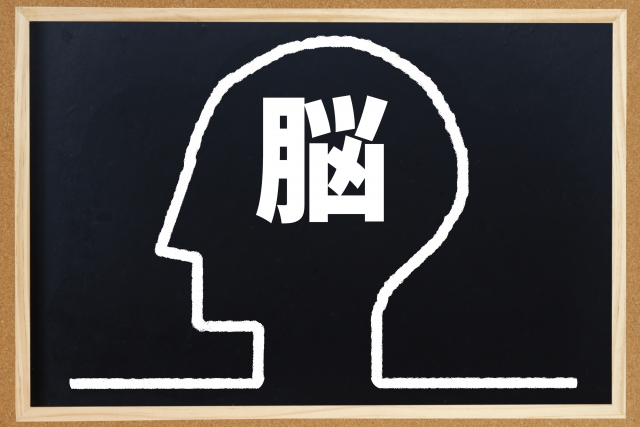
IQ(知能指数)はもともと人間の知能を測るために開発された指標で、論理的思考力や記憶力、言語能力などを数値化したものです。
しかし、動物にそのまま当てはめるのは困難であり、動物の場合は「脳の大きさと体の比率(脳化指数)」や、「学習能力」「問題解決能力」、さらには「道具の使用」や「社会性」など、さまざまな要素をもとに総合的に知能を評価します。
たとえば、カラスは道具を使って餌を取り出すことで高い知能を示す一方で、ナマコのように外的刺激に単純に反応するだけの動物は知能が低いとされます。
ただし、人間の価値観で「賢い・賢くない」を決めつけるのは早計です。環境への適応力や生存戦略の違いも考慮する必要があります。したがって、IQの数値はあくまでひとつの目安として捉えましょう。
脳化指数とは?動物の賢さを測る指標

脳化指数(EQ)は、動物の知能を比較するためによく用いられる指標です。これは脳の重さを体重に対して割り出したもので、EQが高いほど知能も高いとされる傾向にあります。人間はこの数値が最も高く、続いてイルカやチンパンジー、ゾウなどが上位に位置します。
逆に、体に対して脳が極端に小さい動物——たとえばヒトデやクラゲなど——はEQが非常に低く、複雑な学習や記憶を必要としないシンプルな生態を持っています。
こうした動物たちは、厳密な意味での知能は低くても、何千万年も絶滅せずに生き延びてきたという実績があり、ある意味”進化の成功者”とも言えるでしょう。
このように、EQはあくまで動物の脳の相対的な大きさを示す指標であり、そこから知能の傾向を読み取ることができますが、万能な基準ではありません。
「IQが低い」とはどういうことか?判断基準を整理

IQが低い=バカ、というわけではありません。ここでは、以下のような点をもとに“低IQ動物”としています:
- 脳が極端に小さい、または存在しない
- 学習行動が見られない
- 反射的な行動が中心
- 複雑な環境に適応しづらい
IQが低い動物ランキングTOP10

ランキングは、脳の構造・反応性・記憶力などを総合して順位づけしています。詳細は以下の表をご覧ください(推定IQはあくまで目安です)。
| 順位 | 動物名 | 推定IQ(目安) | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1位 | クラゲ | 1以下 | 脳が存在せず、神経網による反射行動のみで生存。環境適応も極めて限定的。 |
| 2位 | ナマコ | 約2 | 中枢神経なし。刺激に反応するだけの単純な構造で、記憶・学習なし。 |
| 3位 | ヒトデ | 約3 | 脳はなく、腕ごとの神経節で制御。行動パターンは反射的かつ単純。 |
| 4位 | カバ | 約10 | 身体能力は高いが、行動に変化や柔軟性が少なく単調。 |
| 5位 | コアラ | 約12 | 偏食で柔軟な判断ができず、環境変化に非常に弱い。 |
| 6位 | ゴリラ | 約15〜20 | 社会性はあるが、研究環境では知能を正しく発揮しにくい。 |
| 7位 | ナマズ | 約16 | 単純な刺激反応で行動。記憶や学習の痕跡は少ない。 |
| 8位 | マグロ | 約18 | 高速遊泳するが行動は直線的で、狩りに戦略性が乏しい。 |
| 9位 | ダチョウ | 約20 | 大型だが脳が小さく、本能による逃走行動が中心。 |
| 10位 | タツノオトシゴ | 約22 | 運動能力も低く、記憶や学習行動がほとんど見られない。 |
実は誤解も多い?「バカな動物」の真実

なぜ低知能とされるのか?環境との関係性
知能が低いとされる動物たちは、シンプルな生態系に生きていることが多く、環境に適応するために複雑な知能が必要ないのです。複雑な社会構造もなければ、捕食者との駆け引きも少なく、ただ本能のままに生きることができる世界に住んでいるのです。
たとえば、海底に生息するナマコは、敵から逃げたり複雑な行動を取る必要がなく、環境変化も緩やかです。そのため、高度な判断力や記憶力が進化しなかったと考えられます。
また、クラゲのように脳すら持たず、刺激に対して反射的に動くだけの構造でも、十分に生き延びている例もあります。
つまり、知能が低いのは“生きるのに必要がないから”であり、それは決して劣っているということではありません。この視点に立てば、単純な構造の動物たちが今も地球上で生き残っているのは、ある意味で「最適な進化」をしているとも言えるでしょう。
実際、何億年もの時を超えて生き延びてきたという事実は、それだけで非常に価値のあることなのです。
ゴリラやチンパンジーは本当にIQが低い?
実際にはとても賢い動物であり、道具を使ったり、社会的な関係性を築いたりする高度な行動も見られます。
しかし、人間のような言語による論理的思考はあまり得意ではないため、IQテストのような実験環境では”低く見える”ことがあるのです。
また、人間の研究者が設計した課題自体が彼らにとって不自然なケースもあり、その結果がそのまま「知能の低さ」と判断されてしまうのは不公平とも言えます。誤解のひとつですね。
「バカに見える=バカではない」行動学の視点
たとえばナマコやヒトデのような動物も、体内の水分を調整する能力や、外敵から身を守る独自の戦略を持っています。
ヒトデは自分の腕を切り離して逃げる“自切”という技を使いますし、ナマコは内臓を吐き出して捕食者から逃れることもあります。
これらの行動は、私たち人間には想像もつかない適応戦略であり、”別の賢さ”を持っている証拠とも言えるのです。
つまり、見た目や反応だけで判断するのではなく、その動物の環境や役割を理解することで、真の知性に触れることができるのです。
見た目にだまされる?強そうで実は…な動物たち

筋肉ムキムキでも知能が低い例
カバやゴリラなど、強そうな見た目とは裏腹に、実際には行動パターンが非常に単純なケースもあります。
これらの動物は、身体的な力に大きく依存する生活様式を持っており、そのため複雑な思考や判断力を駆使する必要が少ないのです。
たとえばカバは縄張り意識が強く、水中での移動能力や攻撃力は抜群ですが、行動自体は反復的で単調です。
一方、ゴリラは社会性の高い動物ではあるものの、その行動範囲や活動内容は非常に限定されており、日々のルーチンに沿った動きが大半です。これは、進化の過程で「力による生存」が優先された結果とも考えられます。
つまり、圧倒的なフィジカルの強さを持っているため、危機を回避するための柔軟な知能を発達させる必要がなかったというわけです。
寒さや環境の変化に弱い動物ランキング
コアラなど、特定の環境にしか適応できない動物は、知能の柔軟性も低い傾向にあります。コアラはユーカリの葉しか食べない偏食ぶりで知られており、食料がなくなれば簡単に絶滅の危機に瀕します。
また、気温の変化や生息環境の変化にも非常に弱く、環境への順応性が低いのです。
このように、生存に必要な選択肢が極端に限られている動物は、日々の選択や判断を迫られることが少ないため、結果として知能の発達が抑えられている可能性があります。
進化の過程で“賢くなる必要がなかった”タイプと言えるでしょう。
強さと賢さのバランスとは何か?
「強さ=知能の高さ」と思われがちですが、実際にはまったく関係ないことが多いです。
たとえば、ライオンやトラなどの肉食獣は非常に強い動物ですが、狩りの際には限られた戦術しか使わず、知能面ではあまり柔軟性がありません。
逆に、プレーリードッグやカラスのように、物理的な力が弱い生き物のほうが、集団で協力したり工夫して行動したりと、知能を活用する場面が多く見られます。
つまり、身体能力が高ければ高いほど知能に頼る機会が少なくなり、それが長い進化の中で知能の発達を抑制する要因となっているのかもしれません。
動物の記憶力とIQの関係性

記憶力の強い動物・弱い動物ランキング
記憶力が強い動物は、状況を学習して行動を変えることができます。
たとえば、イルカは人間とのコミュニケーションや芸の習得を通じて高い記憶力を示すことで知られています。
また、カラスやオウムも、複雑なタスクを記憶し、それに基づいて行動する能力が高いことが研究から明らかになっています。
一方で、記憶が弱い動物は同じ行動を何度も繰り返す傾向があります。例えば、ナマズやクラゲのような動物は、刺激に対する反応は見せるものの、その後の行動に学習の跡が見られにくいです。
これらの動物は、記憶によって行動を変えるのではなく、本能的に反応するだけの構造を持っていると考えられます。
知能が低くても記憶力はある?その意外性
中には、知能が低くても記憶力がそこそこある動物もいます。ハトはその代表例で、単純な行動パターンで生きているように見えるものの、空間認識能力や帰巣本能は非常に優れており、迷子になっても元の場所に戻ることができます。
また、ハトは人の顔を記憶して区別する能力もあり、都市部では特定の人物を避けるような行動を見せることもあります。
このように、「賢くない動物だから記憶力もない」という先入観は誤りであり、それぞれの種が持つ能力は多様であるという事実を再認識させられます。
トレーニングで記憶力は上がるのか?
ある程度までは可能です。たとえば、イヌやネコなどのペットは、繰り返しのトレーニングによってさまざまなコマンドや習慣を記憶することができます。動物園や水族館のトレーナーたちは、報酬と刺激を組み合わせて、動物に複雑な動きを学習させることにも成功しています。
ただし、記憶力の限界は生まれ持った脳の構造にも強く依存しています。いくら訓練を繰り返しても、ある種の動物では一定以上の記憶能力を発揮できないこともあります。したがって、記憶力の伸びしろには生物種ごとに違いがあり、その上限を理解することも重要です。
研究でわかる動物の知能の限界と可能性

動物のIQを研究するための実験と方法
動物の知能を科学的に評価するためには、多様な実験手法が用いられています。代表的なのは迷路実験で、ゴールにたどり着くまでの時間や経路選択の変化を観察することで学習能力や記憶力が測定されます。
ほかにも、複数の選択肢を提示して正解を選ばせる学習テストや、特定のタスクを達成するために道具を使用する能力を調べる実験も行われています。
さらに、最近ではビデオカメラやモーションセンサーを使って、動物の微細な動きを記録・分析する手法も増えており、これにより従来は見落とされていた“考えるプロセス”を捉えることが可能になってきました。
また、報酬や罰を用いた行動心理学的なアプローチも広く活用されています。
実験データが教えてくれる動物の行動パターン
意外にも、多くの動物が“習慣”に強く縛られていることがわかっています。新しい刺激や状況に直面しても、過去に成功した方法やパターンにこだわる傾向が強く、柔軟な思考や創造的な行動ができる動物は非常に限られています。
これは進化的にも当然のことで、自然界では「前と同じやり方で成功する」ことが生存に直結するからです。
しかし一方で、道具の使い方を工夫したり、他者の行動を観察して学ぶ能力を持つ動物も存在し、それらの個体は高い柔軟性を示しています。こうした動物の行動パターンは、知能の構造的な違いを浮き彫りにしてくれます。
未来の動物知能研究と人間との共通点
AI技術の進歩により、動物の思考パターンや記憶の可視化が進んでいます。
たとえば、脳波や神経活動をリアルタイムで記録することで、「どのタイミングで迷い、どこで判断するのか」といった情報まで捉えることが可能になりつつあります。
さらに、機械学習アルゴリズムを使って大量の行動データを分析すれば、動物の“癖”や“学習傾向”を統計的に導き出すことも可能です。
これにより、将来的には人間と動物の知能の違いだけでなく、意外な共通点や類似点が明らかになるかもしれません。今後の研究は、私たちが動物の知性をどのように捉えるかに大きな影響を与えるでしょう。
まとめ:IQが低い動物たちから学べること
私たち人間も含め、すべての生き物にはそれぞれ独自の役割と進化の過程があります。
知能が高い・低いといった基準だけで動物を評価するのではなく、その生物がどのような環境で、どのように生き抜いてきたのかという視点を持つことが大切です。
知能が低いとされる動物であっても、私たちには計り知れない独自の知性や適応力を持っている可能性があります。
だからこそ、動物たちの多様性に敬意を払い、あらゆる命に価値があることを理解することが、真の知性と言えるのではないでしょうか。


