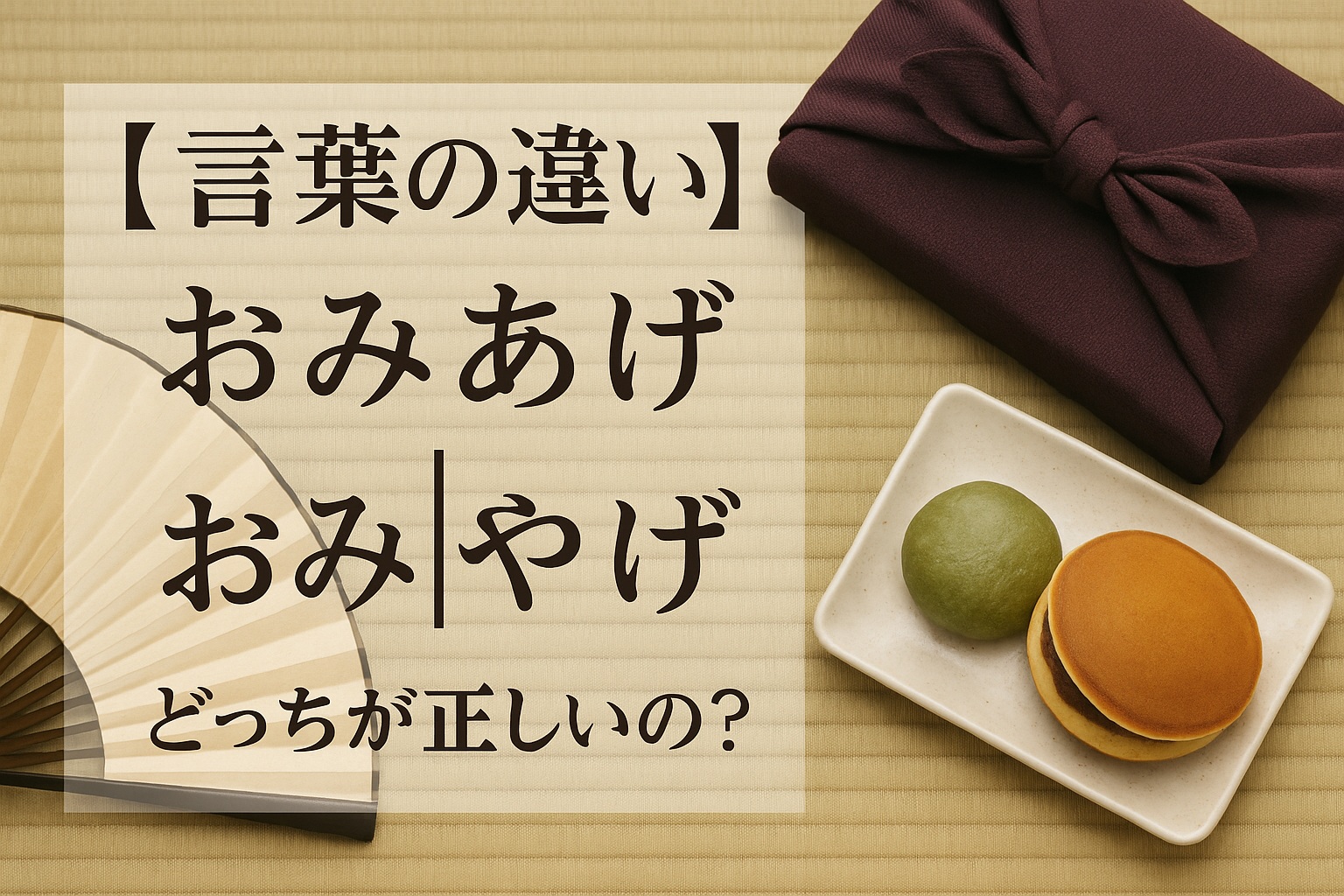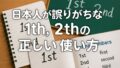旅行から帰ってきたとき、友達や家族にお菓子や名産品を手渡す場面ってありますよね。そんなときに、何気なく「はい、おみあげー!」なんて言っていませんか?
実はその「おみあげ」、ちょっとした言い間違いかもしれません…
普段の会話では違和感なく使っている人も多いこの言葉ですが、果たして「おみあげ」と「おみやげ」、どちらが正しい日本語表現なのでしょうか?
この記事では、その疑問にしっかり答えつつ、「おみあげ」の由来や使われ方についても紹介していきます。
たかが言葉、されど言葉。正しく知っておくことで、ちょっとした場面でも印象が変わることもあるんです!
「おみあげ」と「おみやげ」、正しいのはどっち?
正しい日本語は「おみやげ」
結論から言うと、正しい日本語は「おみやげ」です。
「おみやげ」は漢字で書くと「御土産(おみやげ)」と書きます。
この「御土産」という言葉には、「御」という丁寧語がついており、相手に対する心遣いの気持ちが込められています。
もともとは神社やお寺への参拝後に、その土地に由来するものを家族や知人に持ち帰り、贈るという風習から生まれた言葉です。
「土(つち)」という字が含まれているのは、その土地ならではの名物や特産品を意味しており、旅先の風情をおすそわけするという意味合いがあります。
また、「みやげ」という音は「土産(みやげ)」の読みから来ており、それに敬語表現として「御(お)」がつくことで、今の「おみやげ」という形になったのです。
国語辞典やNHKの放送用語でも「おみやげ」が正しいとされていて、公的な場面では必ずこちらを使うのがマナーとされています。
特にビジネスのシーンや公式な文書、放送メディアなどでは、「おみやげ」という表記・発音が一般的であり、正しい言葉づかいとして認識されています。
「おみあげ」はどこから来た?
一方で、「おみあげ」という言い方は、辞書にも載っていない非公式な表現です。
とはいえ、実際には全国のいくつかの地域で使われており、とくに関西や九州などでは、日常会話の中で自然に使われている場面が見受けられます。地域によっては「おみあげ」があいさつの一部のように馴染んでいることもあるため、その土地に根付いた言い回しともいえます。
このような背景から、「おみやげ」がなまってしまった、あるいは早口で発音しているうちに音が変化して崩れた結果が「おみあげ」になったという説が有力です。
また、耳で覚えた言葉を文字に起こすときに誤変換されることもあり、それが「おみあげ」という表現の普及につながったとも考えられます。
つまり、「おみあげ」は完全に間違いというわけではなく、方言や口語に近いカジュアルな表現として理解されるべきものなんですね。
「おみあげ」が使われる場面とは?

日常会話でよく耳にする理由
友達同士や家族との会話の中で「おみあげ」という言い方を耳にするのは、そのほうが気取らず話しやすいから。
普段のやりとりでは、言葉の正確さよりも、親しみやすさやテンポの良さが重視されることが多いですよね。たとえば、
「はい、おみあげー!食べてねー」
なんてやりとりは、まさにその代表。
このように「おみあげ」は、身近な人とのちょっとした会話の中ではごく自然に使われていて、違和感を持たれにくい言葉になっています。
また、話し言葉は文字とは違って音の印象が大きく、耳から覚えたまま話すことも多いため、「おみあげ」が口癖になっている人も少なくありません。
ただし、これはあくまでカジュアルなシーンでの話。
TPO(時・場所・場合)をわきまえて使い分けるのが、大人としてのマナーです。
ビジネスや書き言葉ではNG?
メールや手紙、仕事関係の文章などでは「おみあげ」はNG。
正式な言葉としては「おみやげ」が正解です。
たとえばビジネスメールや取引先とのやりとりでは、言葉づかい一つで印象が変わります。
「先日のおみやげ、ありがとうございました」
が正しい一文であり、
「おみあげありがとうございました」
だと、どうしても砕けすぎていたり、少し秘しい(稚拙な)印象を与えてしまう可能性があります。
書き言葉では特に、「正確さ」や「信頼性」が求められるため、「おみやげ」を使うのが安全です。
言い間違いを防ぐコツ
「宮(みや)」を意識すると覚えやすい
「おみやげ」の「みや」は、神社やお宮の「宮(みや)」から来ています。
この「宮」は、古くから神様が祀られている神聖な場所を指しており、敬意を表す意味も込められています。
昔は参拝後に、神様に関係する土地のもの、つまりその地域ならではの品物を手土産として持ち帰るという風習がありました。
この背景を知ると、「おみやげ」という言葉には単なる“プレゼント”以上の意味が込められていることがわかります。神様や土地の恵みに感謝して、それを人に分ける行為──そうした日本文化の一端がこの一語に込められているのです。
「みや=神社=土地のもの」と覚えると間違えにくくなりますよ!
さらに、「宮」は「都(みやこ)」とも関係があり、格式ある場所を意味することもあります。
正しい言葉にふれる習慣を
日頃から本を読んだり、ニュースを見たりする中で「おみやげ」という正しい表記を目にする機会が多ければ、多くの場面で自然に使えるようになります。
とくに新聞やNHKなどの公共メディアは、言葉づかいが正確なのでとても参考になります。
最近ではAI校正ツールや辞書アプリも充実してきており、スマホでさっと確認できる時代です。
気になる言葉があったら、すぐに調べて正しい形を確認する習慣をつけるのもおすすめです。
言葉に敏感になると、会話力や文章力も自然とレベルアップしていきますよ!
まとめ:「おみやげ」が正解!
「おみあげ」と「おみやげ」の違い、はっきりしましたか?
- 正しい日本語は「おみやげ」
- 「おみあげ」は一部地域で使われる方言や口語的な表現
- ビジネスやフォーマルな場では「おみやげ」を使うのがマナー
- 会話の相手やシーンによって言葉を選ぶことが大切
言葉は使い分けが大事です。とくに公的なシーンでは、一つの言葉の印象がそのまま自分の印象につながります。
今回のような微妙な違いを知っているだけで、あなたの語彙力や言葉づかいへの意識がぐっと高まりますよ!
「おみやげ」は、ただの土産品ではなく、相手を思いやる日本文化の一部。言葉を正しく使うことも、相手への思いやりの一つかもしれませんね。